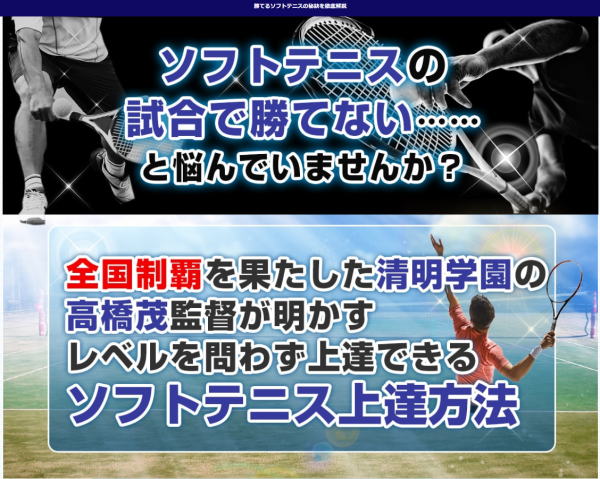ソフトテニスの極意を監修した清明学園の高橋監督の指導法とは?
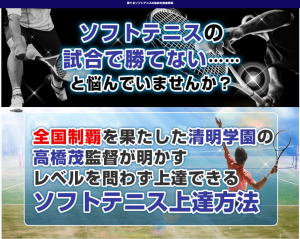
高橋茂監督(清明学園中学ソフトテニス部監督)が「ソフトテニスの極意」などで示している指導法を整理すると、次のような特徴・方針が見えてきます。もちろん、実際には選手の個別事情に合わせて柔軟に変える面もあるでしょうが、指導の“柱”として参考になる点が多いです。
以下、高橋監督の指導法・考え方の主要ポイントを挙げ、それぞれの意図や実践例も交えて解説します。
高橋監督指導法の主な特徴と理念
高橋監督の指導には、次のような特徴・軸があります。
「得点を増やし、失点を減らす」ことを原則とする
監督は、チーム強化の基本軸として「得点を取る力をつける」
「ミスで失点を抑える力をつける」というシンプルかつ明確な目標を
設定して指導していると語っています。
つまり、派手なテクニックばかりを追うのではなく、
「どうすれば点を取れるか」「どこでミスを減らせるか」
を常に問いながら練習を構成するという姿勢です。
科学的・論理的アプローチを重視する
感覚的な指導・経験則だけに頼らず、データや理論、
他競技からの応用も取り入れて体の使い方・動作を分析し、効率を追求します。
たとえば、骨格・筋肉の構造を考えたフォーム調整や、
野球・ボウリングなど異なる競技の動きを
サーブや強打の技術に応用する試みも行われています。
4つの“レバー”(力を伝える要素)に着目する
清明学園の上達ドリル教材では、「頭」「非利き手」「右足」「左足」
という4つの“レバー(レバー作用、力の伝達系)」に着目したトレーニングが紹介されています。
具体的には、
頭(視線・顔・首の使い方)
非利き手(ラケットを持たない手の使い方)
右足・左足(足の蹴り・着地・連動)
という4方向から動きを設計し、それらの動きが相互に作用して
“強いショット”や“安定した構え”がつくられるように指導します
段階的・系統的な練習 → 実戦 → ゲーム形式へつなげる構成
理論や技術解説 → 練習 → ゲーム応用というステップを明確に設け、
選手が実際の試合で技術を使えるように落とし込む指導法をとります。
“解説 → 練習 → 実戦”という流れを意識して、
練習が“ゲームで使える技術”になるよう仕立てる点を重視しています。
弱点の補強・精密性の向上
清明学園の指導では、「ショートボールの打ち分け」「セカンドレシーブのミス防止」
「相手前衛の甘いボレーを得点に変えるパターン」など、
細かい局面ごとの技術や対応力を高めるための練習が多数導入されています。
特に全国大会レベルになると、試合の“継続力”や“局面対応”で差が出やすいため、
こうした細部への配慮がチームの底力を支えていると見られます.
個別最適化と選手段階の意識
全国レベルの選手とこれから伸ばす選手とでは
必要なスキル・重点が異なるという認識を持ち、段階に応じた練習構成を意識します。
また、選手個々の体格・筋力・柔軟性・経験差などを考慮し、
フォーム修正や動きの調整を個別に行うような指導がなされているという記述もあります。
継続・反復と“型”の徹底
基礎動作、姿勢、足使い、ラケット操作など、
反復練習と動きの型(正しいフォーム)を徹底させて、
ミスが出にくい安定性をつくることを重視します。
これは、指導法全体の基盤になっているようです。
また、冬場などシーズンオフ時期にもショートボールなどの分野練習を多く取り入れて、
技術の精度を落とさないようにする例も紹介されています。
メンタル・戦術意識・展開力の重視
単なる「打つ技術」だけでなく、試合展開を読み、相手を崩す工夫、
ゲームプランを立てる発想など、“展開力”や“闘い方”に対する教育も含まれます。
たとえば、「試合でどのプレーをすべきか/すべきでないかをパターン化して把握する」
「得点パターンを練習で体得する」などのアプローチが紹介されています。
実践例・練習内容の一部
上記の指導方針を具体化した練習メニュー・ドリル例も、
公開教材等から垣間見えます。
以下はその一部です。
領域 頭・視線・顔の使い方
練習・ドリル例 顔を残す/顔を背ける動作、あごを固定する動きなど
狙い・効果 バランス崩れやすい局面でのショット安定性を高める
領域 非利き手使い
練習・ドリル例 ラケットを持たない手を使ったエネルギー伝達ドリル
狙い・効果 非利き手を使うことで全体の動作を滑らかにする
領域 足の使い方(右足/左足)
練習・ドリル例 蹴り動作、つま先使い、前足荷重、壁の反発を使う原理の応用など
狙い・効果 下半身から上半身へ力を伝える効率を高める
領域 両足連動ショット
練習・ドリル例 リズムスマッシュ、ランニングショット、モーグルショットなど
狙い・効果 足の連動性を使ってパワーと速さを両立させる
領域 ショートボール打ち分け
練習・ドリル例 冬場重点練習、変化をつけたショートボール練習
狙い・効果 相手の前衛への攻撃パターンを多様化させる
領域 得点パターン練習
練習・ドリル例 相手前衛の甘いボレーを確実に得点にするパターン練習、終盤対応パターンなど
狙い・効果 勝負どころで得点を取る力を鍛える
領域 ミス防止練習
練習・ドリル例 セカンドレシーブミス低減練習、安定性を重視した構え・返球練習
狙い・効果 相手ミスを誘う中で失点を抑える力をつける
これらの練習は、ただ“ショットを打つ反復”ではなく、
「どの状況でどの動きをすればいいか」を設計しており、
選手が“状況判断・身体の使い方”を同時に身につけられるように設計されている点が特徴です。
強みと留意点(メリット・課題)
高橋監督の指導法には、多くの強みがある反面、
実践するには注意すべき点もあります。
強み・有効性
技術・動作を論理的に分解し、
個別最適化して指導できるため、選手それぞれの弱点改善につながる。
試合展開を重視した指導により、
技術が「使える武器」として定着しやすい。
得点と失点を明確に基準とすることで、
指導の評価・改善がしやすい。
練習時間が制限される学校現場でも、
効率的に技術を伸ばす設計が可能。
留意点・実施課題
論理的・細部重視の指導は、
指導者側に高い技術理解力が要求される。
細かい動きの指導が多いため、
選手にとって意識項目が多く感じられ、混乱する可能性もある。
練習の設計・準備が複雑になりがちで、
時間管理や体力配分に注意を要する。
指導方針をそのまま“丸写し”しても、
選手層・環境・目的が異なれば合わないこともあるため、
カスタマイズ力が求められる。
前衛の1週間メニュー「ソフトテニスの極意」は
前衛の練習方法「ソフトテニスの極意」は
スマッシュを安定させる1週間練習スケジュール「ソフトテニスの極意」
ソフトテニス一人で練習「ソフトテニスの極意」
ソフトテニスが上手くなる方法「ソフトテニスの極意」
初心者が上達しにくい理由3選「ソフトテニスの極意」
独学で壁を感じた時に見直すポイント「ソフトテニスの極意」で解決できる部分を紹介
「DVD教材とYouTubeの違い」で有料教材の価値を説明してから紹介する(ソフトテニスの極意)
スマッシュが苦手な人がまず取り組むべき練習(ソフトテニスの極意)は
サーブが苦手な人がまず取り組むべき練習(ソフトテニスの極意)は
ソフトテニスの極意はストロークが不得意わたしでも大丈夫?
「ソフトテニスの極意」で解決できる部分を紹介
ソフトテニスの極意を監修した清明学園の高橋監督の指導法とは?
ソフトテニスの極意はショットが不得意わたしでも大丈夫?
ソフトテニスの極意は中級者のわたくしに適しているか
ソフトテニスの極意は初心者のわたくしに適しているか
ソフトテニスの極意の評判は